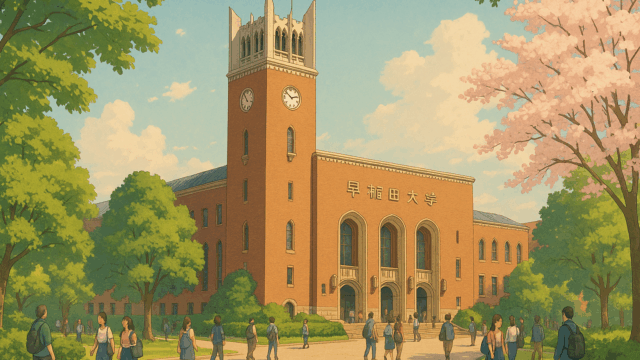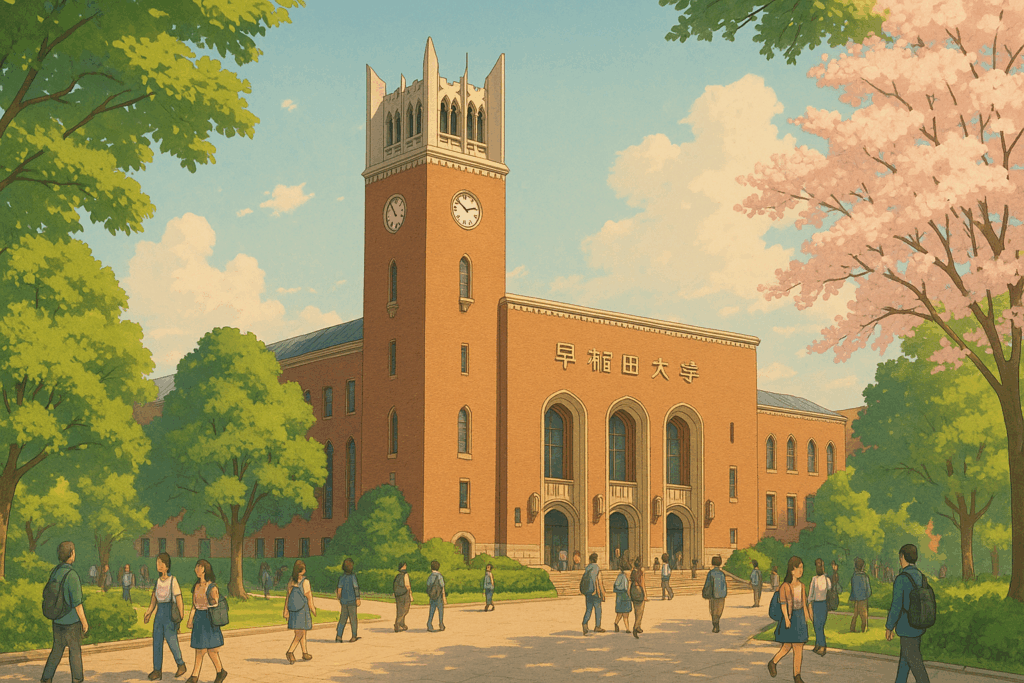
早稲田大学国際教養学部の英語入試徹底分析(2022〜2025年度)と2026年度対策
早稲田大学の国際教養学部(School of International Liberal Studies:SILS)は授業のほとんどを英語で行うため、英語の個別試験でも高いレベルの読解力・表現力が求められます。2021年度入試からReadingとWritingの試験が分かれ、Reading90分・Writing60分で合計80点の配点となり、外部英語検定試験から最大20点が加算されます。共通テスト(国語50+地歴/数学/理科50=100点)と合わせて100点満点で選考が行われます。以下では2022〜2025年度の英語入試を分析し、2026年度に向けた対策をまとめます。
1. 基本情報と出題構成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験時間・配点 | Reading90分+Writing60分=80点外部英語検定から最大20点加算共通テスト100点と合計100点で選考 |
| Readingの問題構成 | 長文読解3題(各約1,000語)設問は段落要約選択、語句言い換え、内容一致/不一致、語句挿入など選択肢が10個前後ある大問もあり |
| Writingの問題構成 | 大問1・2:自由英作文(2題)大問3:日本語での要約1題自由英作文は近年、グラフや図表・データを説明して意見を述べる問題が出る場合がある |
| 出題量 | Reading部の総語数は約3,000〜3,200語1題当たり約20問が出題され、語句・表現・内容理解など多様な設問が含まれる |
| 外部試験加算 | 英検1級は20点、準1級は14点など階級別に点数が決まる外検による得点調整は2021年から国際教養で実施されなくなり、合格最低点が25〜30点ほど上がった |
2. Readingの特徴
文章量と難易度の高さ
長文は論説・歴史・社会問題など幅広いテーマから出題され、単語難易度も高い。2023年度の総語数は約3,180語で、各文章に20問前後の設問が付いた。社会科学部よりは少ないが、制限時間内に読み切るには速読力と読解力が必要。
内容一致問題の選択肢が多い
1つの設問で10個から4つ選ばせる形式など選択肢数が多く、本文と選択肢を行き来するため時間を消耗する。出題者は細部への注意と論理的な根拠付けを求めている。
語句挿入・語句言い換え
難解な語の同義語や文脈に合う語句を選択する問題も多い。
3. Writingの特徴
自由英作文
大問1・2は約100〜200語程度の自由英作文で、近年は「カジノ開設への賛否」「ボランティア活動の義務化」「タコスの歴史」「ドッジボール禁止是非」など社会問題や日常生活に関するテーマが出題された。1題はグラフやデータを読み取り、自分の意見や考察を英語で述べる形式になることが多い。
日本語要約
大問3では短い英語文を日本語で要約する問題が出される。文字数の制限はないが、要旨を端的にまとめる能力が求められる。
4. 過去4年(2022〜2025年度)の傾向
国際教養学部の英語試験は毎年大問数や構成はほぼ同じだが、長文や設問の難易度は年度によって変化する。
| 年度 | 難易度 | 特徴的なテーマ |
|---|---|---|
| 2021年度(参考) | 標準的 | Readingは標準的な長文問題が中心語彙問題で “perennially”(長年にわたって)や “cut one’s teeth”(経験を積む)など難しい語 |
| 2022年度 | やや難 | 自由英作文:「高校生にボランティアを義務付けるべきか」グラフ読み取り:「プラスチック廃棄の管理状況」要約:「狩猟採集社会の成功」 |
| 2023年度 | 難化 | 長文Ⅰが特に難しく、全体として難化自由英作文:「ドッジボールの全面禁止に反対か賛成か」グラフ比較:GDP水準と成長率から未来を予測要約:トンガの海底火山噴火 |
| 2024年度 | 平年並み | 2023年より易化、歴史的難度から平年並みに自由英作文:「タコスの歴史」「大阪へのカジノ誘致への賛否」グラフ解釈:「エネルギー消費量の推移」 |
4.1 2025年度入試問題の特徴
2025年度の国際教養学部英語は、Reading 90分(配点80点)・Writing(配点非公開)の構成で実施されました。
Reading部分の詳細
全体構成:
- 長文読解3題(長文I、II、III)
- 総語数:約3,200語(過去5年間で標準的な分量)
- 設問数:各長文に約20問前後
長文I:言語と思考に関する論説文
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 言語が思考に与える影響(サピア=ウォーフ仮説) |
| 難易度 | 標準 |
| 設問形式 | パラグラフの要旨選択、内容不一致選択(2つ)、語彙問題 |
| 特徴 | 選択肢に日本語の説明「英文は再照的な文になっての思考パターンについて」など、思考プロセスの説明が含まれる |
長文II:言語学習に関する研究
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | クローゼド・キャプション(字幕)を使った言語学習の効果 |
| 難易度 | やや難 |
| 設問形式 | 内容不一致選択(1つ)、パラグラフの要旨選択(3つ)、同義語選択 |
| 特徴 | 実証研究のデータと結論を読み解く力が必要。「非母語話者」「母語話者」などの専門用語が登場 |
長文III:歴史と言語に関する論説文
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 歴史的言及と歴史との関係性 |
| 難易度 | 標準 |
| 設問形式 | パラグラフの要旨選択(2つ)、同義語選択、内容不一致選択(2つ)、下線部の言葉レベル解釈 |
| 特徴 | 「文章から判断すれば解答可能である」「主体に比べ→選択肢の分量が大幅に減少してわかりやすくなった」との分析 |
2025年度の総評:
- テーマの統一性 — 3つの長文すべてが「言語」に関連するテーマで統一
- 設問形式の多様化 — パラグラフ要旨選択が多く、内容理解の精度が問われる
- 難易度の安定 — 長文IIがやや難だが、全体として平年並みの難易度
- 日本語での説明 — 設問や選択肢に日本語の説明が含まれる点が特徴的
4.2 2025年度Writing問題の特徴
2025年度のWriting部分は60分(配点50点)で、例年通り自由英作文2題、日本語要約1題の3題構成でした。
Writing問題の詳細
大問I:自由英作文(大学教育の目的)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 大学教育の目的について |
| 語数 | 指定なし(解答欄のスペースから150-200語程度と推定) |
| 設問内容 | 「短い英文を読み、その内容についての自分の意見とその理由を英語で述べる」 |
| 提示文 | 大学教育は職業訓練のためか、心と精神を解放するためか、という議論 |
| 難易度 | 標準 |
出題文の要点:
- 15センチ×10行の解答欄
- 大学教育の目的は「心と精神を解放すること」か「職業訓練」かという二項対立
- 受験生は立場を明確にして論じる必要がある
大問II:自由英作文(グラフの説明)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 高所得国・低所得国における家計の教育支出の割合を示したグラフの分析 |
| 形式 | グラフを見て、観察される傾向を説明する |
| 難易度 | やや難 |
グラフの内容:
- 15カ国・低所得国15カ国における家計の教育支出割合を示す
- そこから分かる傾向を説明する問題
- 解答欄は15センチ×12行
- グラフが表している内容の分析と考察が求められる
大問III:日本語要約
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 言語教材の病気が健康と語彙の獲得に与える影響 |
| 語数 | 300〜400語程度の英文を読み、その内容を日本語で要約 |
| 解答形式 | 解答欄は15センチ×8行 |
| 難易度 | 標準 |
要約文の内容:
- 文章全体の構成をつかみやすい内容
- 英文の情報量が多く、必要な情報を見極めて的確に要約する能力が問われる
- 制限時間内に簡潔にまとめる力が必要
合格のための学習法(2025年度版)
2025年度の問題を踏まえた具体的な対策:
自由英作文対策:
| 対策項目 | 方法 | 2025年度の教訓 |
|---|---|---|
| 意見論述型 | 賛否両論の整理<br>明確な立場表明 | 「大学教育の目的」のような哲学的テーマへの準備 |
| グラフ説明型 | データの比較表現<br>傾向の分析力 | 高所得国vs低所得国のような対比構造の把握 |
| 語数調整 | 150-200語での論述練習 | 解答欄のスペースに合わせた分量調整 |
日本語要約対策:
| 対策項目 | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 情報の取捨選択 | 主要論点の抽出<br>具体例の省略 | 300-400語を8行にまとめる訓練 |
| 簡潔な日本語表現 | 冗長な表現を避ける<br>的確な用語選択 | 「言語教材」「語彙獲得」など専門用語の適切な訳 |
| 時間管理 | 15-20分での完成 | 英文理解5分、構成5分、執筆10分 |
5. 総合的な傾向
長文Ⅰが難しくなりやすい
2023年度は特に難しく、長い文と専門的な内容で差が付いた。2024年度は平年並みに戻ったが、例年Ⅰは他の大問より難しい傾向がある。
自由英作文は標準レベルでスコア源にできる
Writingの問題は国公立大の自由英作文と類似しており、適切な構成や英文表現を身につければ高得点が狙える。
テーマは社会問題や身近な話題まで幅広い
ボランティアの義務化、UBI(ベーシックインカム)、スポーツ禁止の是非、エネルギー消費やGDPなど様々なテーマが出題されている。これらに対して自分の意見や考察を論理的に述べる力が必要。
要約問題は毎年安定して出題
Readingで段落ごとに要点を捉え、Writingパートで端的にまとめる練習がすべての大問に役立つ。
6. 2026年度に向けた戦略と学習法
6.1 出題形式の予想
過去4年の傾向から、2026年度も大きな変更はないと考えられる。Reading3題・Writing3題の構成は継続され、長文Ⅰが難度差別化の役割を担い、自由英作文と日本語要約は標準レベルで実力を発揮できるセクションになるだろう。外部英語検定の得点加算制度も続く見通しであり、準1級以上の取得は合格の後押しとなる。テーマは社会問題やデータ解釈など時事性の高いものが出題される可能性が高いので、幅広い知識と意見形成が不可欠だ。
6.2 時間配分と解答順
| セクション | 時間配分 | ポイント |
|---|---|---|
| Reading(90分) | 各長文30分 | 長文Ⅰが難しい場合でも30〜35分以内に切り上げ内容一致問題では最初に選択肢の内容を覚える各設問の根拠位置をメモしながら読み、戻り読みを減らす |
| Writing(60分) | 自由英作文各20分日本語要約20分 | グラフ説明では、データの比較ポイントとトレンドを明確に要約では本文の主張・理由・結論を3〜4文でまとめる |
6.3 読解力向上の対策
| 対策項目 | 方法・教材 | ポイント |
|---|---|---|
| 速読と構造理解 | パラグラフリーディング『やっておきたい英語長文500・700』 | 段落の役割(抽象/具体)を意識タイマーを使い無声で素早く読む訓練 |
| 内容一致問題対策 | 選択肢先読み法法学部の過去問活用 | 選択肢を最初に読み内容を覚える本文を読み進める際に該当箇所で判断 |
| 語彙強化 | 『英検パス単準1級』『シス単』『ターゲット1900』 | 準1級レベルまでの語彙を完璧に未知語の意味推測力を養う |
| 長文演習 | 『英語長文ポラリス3』『難関大英語長文講義の実況中継』 | 700~1000語の問題集で毎日長文を解く法学部や社会科学部の長文問題も活用 |
6.4 英作文・日本語要約の対策
| 対策項目 | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| テンプレート習得 | 序論・本論2点・結論の構成定型表現の暗記 | “I believe that…”、”In conclusion…”などグラフ説明の導入句も準備 |
| 論理的な主張 | 新聞記事やTED Talks活用賛否両論の整理 | 社会問題に対する意見を持つ理由を2〜3点挙げる練習 |
| 日本語要約 | 段落ごとの要約練習主旨→理由→結論の順 | 指定語数がないため端的に表現冗長にならないよう注意 |
7. 2026年度の予想とアドバイス
問題構成は継続
Reading3題・Writing3題の構成が続くと予想される。外検加算制度も継続される見込み。2026年も長文Ⅰが難問になる可能性が高いため、時間配分と難問スキップの勇気が重要となる。
テーマの広がり
過去の自由英作文が社会問題・文化・科学など多彩だったように、2026年もAI・エネルギー・環境問題など時事的なテーマが出る可能性がある。日頃から英字新聞・論説記事やデータ解説に触れ、自分の意見を英語で述べる訓練を積んでおきたい。
外検対策を優先
準1級以上を取得すると最大14〜20点の加算があり大きなアドバンテージになる。早めに取得して他科目学習に時間を回すことを推奨する。
8. おわりに
国際教養学部の英語入試は、早稲田大学の中でもトップクラスの文章量と難易度を誇る。その一方で、構成は毎年ほぼ同じであり、徹底した過去問演習と基礎力の強化で攻略が可能である。2026年度入試に向けては、長文速読と論理的思考、豊富な語彙、そして自由英作文・日本語要約のスキルを鍛え、社会問題への関心を持って意見を表現できるよう準備しておこう。
2025年度の国際教養学部英語は、「言語」という統一テーマで出題され、より学術的・専門的な内容となりました。この傾向は、国際教養学部が求める学生像「英語で専門分野を学ぶ力」を直接的に測る試験へと進化していることを示しています。
2026年度受験生は、単なる英語力だけでなく、英語で学術的内容を理解し、論理的に思考する力を養う必要があります。特に:
- 専門分野の基礎知識を英語で習得
- 学術論文の構造と論理展開の理解
- データや実証研究の読み取り能力
- パラグラフごとの要旨を瞬時に把握する力
これらの能力は、入学後の授業でも必要となるスキルです。早めの準備で、合格とその先の成功を目指しましょう。