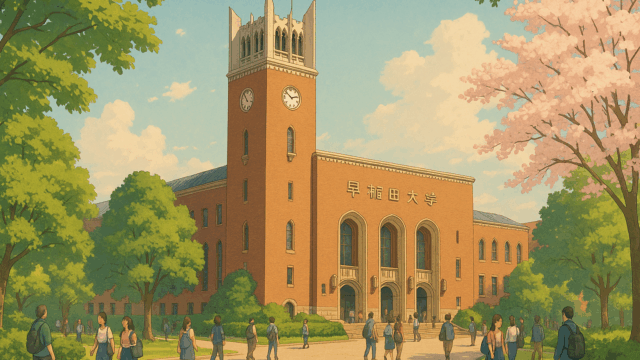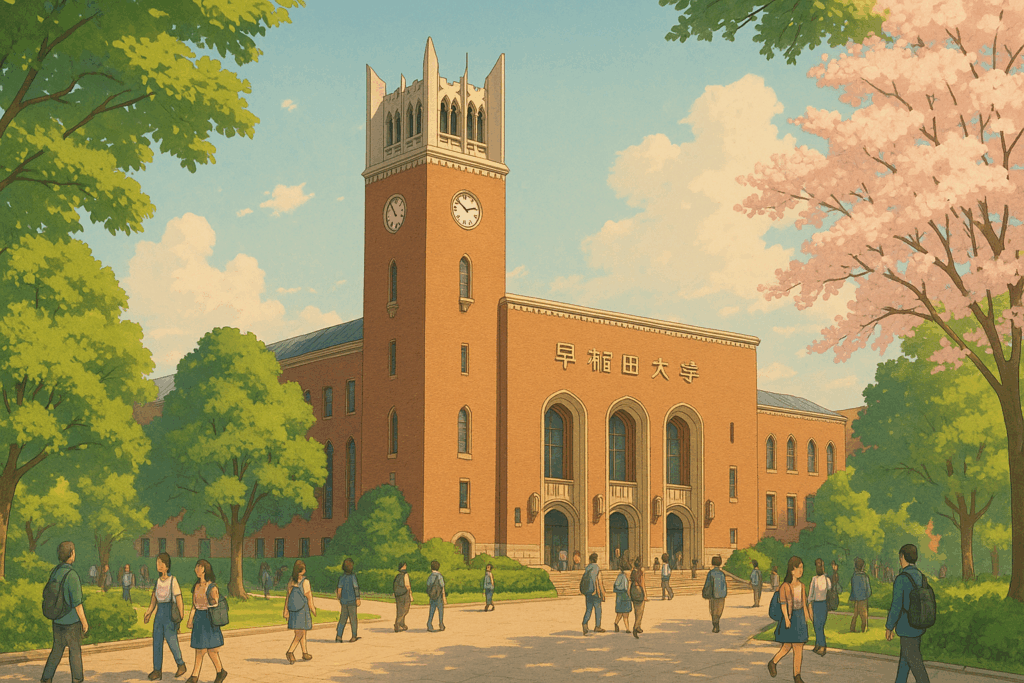
早稲田大学文学部英語入試(2022〜2025年度)徹底分析と2026年度対策
早稲田大学文学部の英語は、長文読解、文挿入、会話、要約という複数の形式を組み合わせた90分試験です。配点は英語75点・国語75点・選択科目50点の3科目計200点で、英語の比重が最も高くなっています。合格最低点は近年130点台前半で推移し、英語平均点は約40点(得点率53%)と他科目より低いため、英語で差を付けることが重要です。以下では過去4年(2022~2025)の傾向を分析し、2026年度に向けた戦略をまとめます。
1. 試験構成と特徴
文学部・文化構想学部の英語は、5つの大問で構成されています。出題形式は文化構想学部と共通ですが、文学部の答案は難易度の変動が大きく、実力+運の要素が入り交じります。以下の表は大問構成とおおよその語数・時間配分です。
| 大問 | 内容 | 推定語数/形式 | 推奨時間 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| I | 長文読解(空所補充) | 2つの長文を読んで空所に入る単語を選ぶ。難単語が出るが文脈から推測可能 | 約25分 | 運要素が強い。語彙・文法で解ける問題は確実に取り、解けない問題は深追いしない |
| II | 長文読解(内容一致) | 3つの短めの長文(200〜500語)を読み、内容一致を問う | 約20分 | 語彙はやや易。手際よく読み、得点源にする |
| III | 長文読解(文挿入) | 1つの約700語の長文の空所に8つの選択肢から7つを挿入 | 約15分 | 最難関。パラグラフリーディングで段落の要旨を捉え、前後の時制・代名詞などで選択肢を絞る。演習必須 |
| IV | 会話文(空所補充) | 会話文に7つの空所があり、13選択肢から適語を選ぶ | 約10分 | 文脈理解と語法力が求められる。難単語よりも正しい構文と語法が鍵 |
| V | 要約英作文 | 約250語の短い英文を読んで与えられた書き出しに続けて4〜10語で要約する。本文から3語以上連続した語句は使用不可 | 約10分 | 読解力と言い換え力が必要。書き出しに続く内容を見つけ、別表現で記述 |
試験全体で読む英文は約2400語です。多様な形式に対応するため、語彙・文法力、速読力、要約力を総合的に鍛える必要があります。
2. 2022〜2025年度の傾向比較
近年の難易度をまとめると以下の通りです。いずれの年も大問構成は同じですが、難易度に波があります。なお大問V(要約)のテーマは社会問題・環境・教育など時事的な内容が多くなっています。
| 年度 | 講評 | 大問I | 大問II | 大問III | 大問IV | 大問V | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 標準 | 標準 | やや易 | やや難 | 標準 | 標準 | AIや環境問題など時事的テーマが増加。文挿入は依然として難しい |
| 2024年 | 易〜標準 | やや易 | やや易 | 標準 | 標準 | 標準 | 全体的に平年より易化し、語彙レベルも穏やか。高得点を狙いやすいがケアレスミスに注意 |
| 2023年 | 難化 | やや難 | やや難 | 標準 | 標準 | やや難 | 長文テーマが抽象的で選択肢の差が微妙。語彙・背景知識が必要 |
| 2022年 | 標準 | 標準 | 標準(Bはやや難) | 標準 | 標準 | 標準 | 全体的にオーソドックス。基本事項を押さえれば対応できる |
このように、難易度は年度によって上下します。2023年は語彙・背景知識が問われて難化し、2024年は易化しました。大問IとIIIは年ごとの難易度の振れ幅が大きく運要素が強いと指摘されています。取りやすい大問II・IVで確実に得点し、難問に時間を取られない戦略が有効です。
3. 2026年度への予測と戦略
3.1 出題形式は基本的に継続
• 2022〜2025年の出題形式はほとんど変化せず、長文読解3題・会話・要約という構成が定着しています。
• 2026年度も同形式が継続する可能性が高いと考えられます。
• 出題テーマは社会・環境・教育など幅広いですが、時事的な内容が多くなる傾向があるため、ニュースや英語エッセイを読む習慣を付けましょう。
3.2 際立つ語彙力と速読力が鍵
• 難易度が上がる年度では難単語が正答の鍵になることが多いです。
• 英検準1級レベルの語彙を習得し、長文中の難語を文脈から推測する力を養っておきましょう。
• 文章量が多いため、段落ごとに主張を捉えるパラグラフリーディングを練習し、速読力を高めることが求められます。
3.3 大問III(文挿入)と大問V(要約)が差を生む
• 大問III — ダミーの選択肢が1つ含まれ、正解の7文を選ぶ独特の形式です。文脈や時制・代名詞・ディスコースマーカーで選択肢を絞る訓練が必須です。パラグラフリーディングとディスコースマーカーの理解ができれば処理速度が上がります。
• 大問V — 要約は4〜10語で指定された書き出しに続ける形式で、本文の連続した3語を使用してはいけません。指示に沿った主題を抽出し、別表現に言い換える語彙力が必要です。2026年度はここで差がつく可能性が高く、日頃から英語の要約練習を行いましょう。
3.4 時間配分と解答順序
推奨される時間配分は以下の通りです:
• 大問I(25分) — 解ける問題を素早く解き、難問は飛ばす。
• 大問II(20分) — 読みやすいので得点源にし、確実に解答する。
• 大問III(15分) — パラグラフリーディングで大意を把握しながら文挿入を処理。
• 大問IV(10分) — 会話文は文脈と語法で論理的に選択。
• 大問V(10分) — 要約問題は文章の主題を見つけ、別表現で書き換える。
順序としては大問II→IV→V→I→IIIのように解きやすいものから進めるのも有効です。運要素の強い問題に時間をかけすぎず、得点源を確実に取りましょう。
4. 推奨教材一覧
4.1 語彙・文法教材
| 学習領域 | 教材 | 特徴・使い方 |
|---|---|---|
| 語彙(基礎〜中級) | 『英検でる順パス単準1級』 | 文学部に必要な語彙の土台を作る。1日100語×10周を目標に |
| 語彙(上級) | 『出る順で最短合格!英検準1級英単語EX』 | 難単語対策。文脈推測力も同時に養う |
| 文法(基礎) | 『ネクステージ英文法・語法問題』 | 基本文法を網羅的に学習。苦手分野を重点的に |
| 文法(演習) | 『頻出英文法・語法問題1000』『実力判定英文法ファイナル問題集』 | 入試レベルの演習。時間を計って解く |
4.2 長文読解・文挿入対策教材
| 学習領域 | 教材 | 特徴・使い方 |
|---|---|---|
| 長文読解(基礎) | 『やっておきたい英語長文500』『イチから鍛える英語長文500』 | 500語レベルから段階的に学習 |
| 長文読解(標準) | 『やっておきたい英語長文700』『イチから鍛える英語長文700』 | 文学部レベルの語数に対応 |
| 文挿入対策 | 『パラグラフリーディングのストラテジー1・2』 | 論理展開の読み方を習得 |
| 過去問演習 | 文学部・文化構想学部過去問5〜10年分 | 文挿入問題を重点的に演習 |
4.3 会話文・要約対策教材
| 学習領域 | 教材 | 特徴・使い方 |
|---|---|---|
| 会話文 | 『ネクステージ』会話表現編『英文法ファイナル問題集難関大学編』 | 日常会話表現と語法を習得 |
| 会話文演習 | 同志社大学などの過去問 | 会話問題が豊富な大学で練習 |
| 要約(基礎) | 『英文要旨要約トレーニング』 | 要約の基本的な型を学ぶ |
| 要約(実践) | 『英文要旨要約問題の解法』 | 文学部形式の要約に特化 |
4.4 語彙の覚え方
• 単語帳を「繰り返し・声に出して」覚えることが重要です。
• 5〜10秒で和訳が出るまで反復し、1日数回高速で回します。
• 意味・品詞だけでなく、例文や派生語も意識して覚えると長文読解や要約で活用しやすいです。
• 文法問題集でカバーされないミスをノートにまとめ、自分だけの弱点集を作ると効果的です。
5. 勉強計画例
5.1 基礎期(4〜8月)
• 英検準1級レベルの単語帳と『ネクステージ』で語彙・文法基礎を完成。
• 長文は300〜500語の易しい素材でパラグラフリーディングを練習。
• 週2〜3回、要約の基礎練習を開始。
5.2 演習期(9〜11月)
• 500〜700語の長文を週に5〜6題解く。
• 文化構想学部と文学部の過去問で文挿入と要約に慣れる。
• 要約は必ず添削を受け、表現の幅を広げる。
• 会話文問題を週2〜3題のペースで演習。
5.3 直前期(12〜試験直前)
• 過去問を時間を計って解き、II・IV・Vを先に解く練習を行う。
• 苦手な語彙・文法をノートにまとめ、暗記の確認を続ける。
• 時事問題に関する英文を読み、背景知識を補強。
6. まとめ
• 試験形式は5大問で長文読解3題・会話・要約から構成され、英語75点の比重が高い。
• 大問IとIIIは難易度の揺れが大きく、2023年は難化、2024年は易化しました。大問IIとIVを確実に取り、大問Vの要約で差を付けましょう。
• 2026年度も同形式が継続する可能性が高く、語彙力・速読力・要約力が合否を左右します。英検準1級レベルの語彙を習得し、パラグラフリーディングや要約の練習を積むことが重要です。
早稲田大学文学部の英語は、難易度の変動があるものの対策を積めば必ず高得点を狙える試験です。計画的に学習し、英語でリードして合格を目指しましょう!