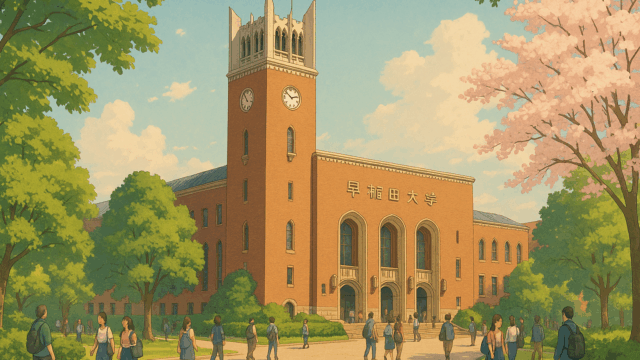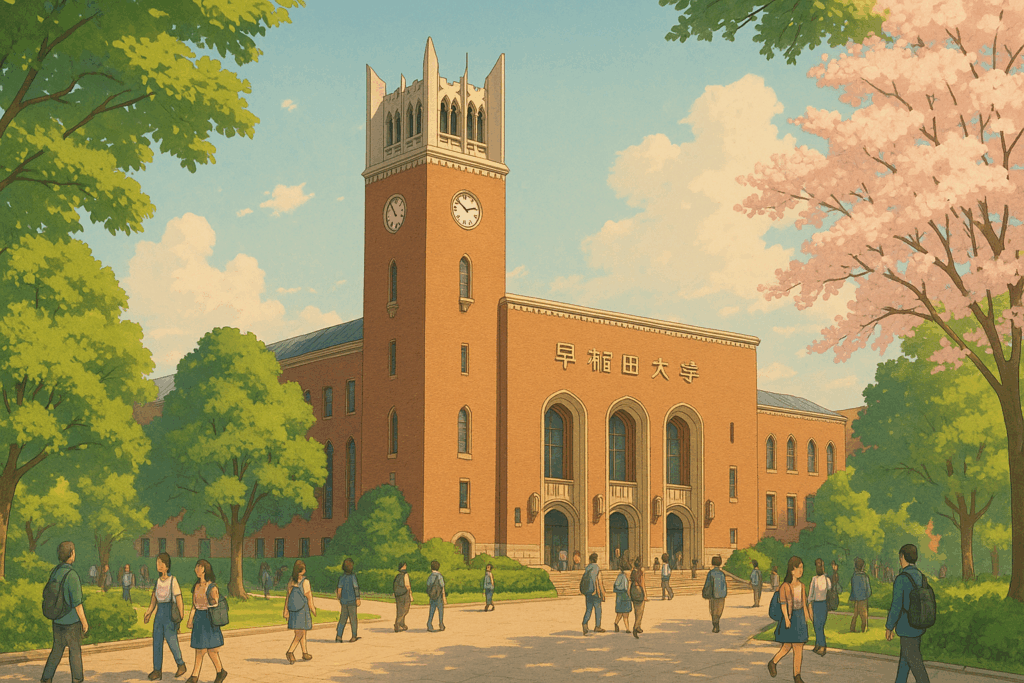
早稲田大学文化構想学部英語入試(2023〜2025年)徹底分析と2026年対策
早稲田大学文化構想学部の一般入試では、例年90分で英語・国語・社会の3科目が課され、英語の配点は75点で国語と同等の比重です。近年は4技能試験(TEAPや英検など)のスコアを利用する方式も併願でき、条件を満たすと国語・社会のみで判定されます。以下では2023〜2025年までの過去問題を詳しく分析し、出題傾向と攻略法、2026年の予想、セクション別の時間配分、学習法をまとめます。記事末尾にはおすすめ教材一覧も掲載します。
1. 入試概要と出題形式
文化構想学部の英語試験は大問5題から構成されます。各大問の目安時間と概要を次のように整理しています。
| 大問 | 内容 | 問題数(目安) | 推奨時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 大問Ⅰ | 長文の空所補充(300語程度の英文が複数) | 約14問 | 25分 | 文脈を読んで適切な語句を選ぶ。難単語は少ないが、読解速度が問われる。 |
| 大問Ⅱ | 長文読解(200〜600語の英文3本) | 約10問 | 20分 | 内容一致問題。文章自体は標準的だが、選択肢は言い換え表現が多い。 |
| 大問Ⅲ | 長文脱文補充(論理展開に合う一文を選ぶ) | 約7問 | 15分 | 論理構造把握が鍵。選択肢が多く(8つ)、時制やディスコースマーカーを手がかりに絞り込む。 |
| 大問Ⅳ | 会話文補充 | 約7問 | 10分 | 会話独特の口語表現が出題。熟語・前置詞のイメージを踏まえつつ文脈推測が必要。 |
| 大問Ⅴ | 英文要約(英文で4~10語程度) | 1問 | 10分 | 与えられた英文の要点を自分の言葉でまとめる。語句の直接引用は禁止。 |
この5題構成は文学部とほぼ同じで、近年の傾向として英文の数が多い(約9本)こと、各長文が200〜600語と中程度の長さであることが特徴です。合格ラインは7.5〜8割であり、余裕をもって8割以上を目指すべきとされています。
2. 過去3年(2022〜2024年度)および2025年度問題の傾向
2.1 年度別難易度の概略
各年度の講評をもとに、近年の難易度と特徴をまとめました。
| 年度(入試実施年) | 大問Ⅰ — 長文空所補充 | 大問Ⅱ — 長文読解 | 大問Ⅲ — 脱文補充 | 大問Ⅳ — 会話文 | 大問Ⅴ — 要約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年実施 | 標準的。前年よりやや難化 | 標準 | 標準 | やや難。難しめの熟語が出題 | 標準 | まとめ全体として標準レベル |
| 2024年実施 | 標準。難問もあるが消去法で対応可 | 標準 | 標準だが文章難易度が高く、答えの決め手が少ない | やや易 | 標準 | 全体として長文の質がやや難化 |
| 2025年実施 | 標準。難しい語もあるが消去法で対処可 | 標準 | 標準。文章が難しめだが代名詞や接続表現が手がかり | 標準。熟語「run ~ by …」など難語も含むが差はつかない | 難化傾向。時制の変化と最終段の主張を含める必要があり、要約力が問われた | 5題目の要約が特に難しくなり、要約力の重要性が増した |
2.2 過去問から見える共通点と変化
• 形式は安定している — 2010年代から5題構成がほぼ変わらず、脱文補充と英語要約が特色です。毎年「標準レベル」の長文問題が中心であり、難しい語が出る年でも消去法で対応できるようになっています。
• 要約問題の難化 — 2025年では要約の難易度が上がり、時制に合わせて「これまでの展開」と筆者の最終主張を9語前後でまとめる必要がありました。今後も要約力が差をつける問題になると予想されます。
• 選択肢の言い換え — 長文読解では選択肢が本文と同じ単語を使わず言い換える傾向があり、同義語や反意語の知識が必要です。
• 脱文補充は論理マーカーが鍵 — 選択肢が8個と多く、時間との勝負。時制、代名詞、接続詞、固有名詞、主語の一致を確認するのが効率的です。
• 会話問題は口語表現に注意 — 定番の熟語以外に「run ~ by …」など慣れない表現が出る年もありますが、ポイントは文全体の意味を推測することです。基本表現を覚え、知らない表現は前置詞や動詞から推測する練習をしておくと良いでしょう。
• 語彙・背景知識の影響 — 2025年の大問Ⅰでは “repudiate(否定する)” や “denigrate(中傷する)” など難単語が出ました。また “Adam and Eve’s Fall” の知識があると解きやすいとの講評もあり、文化・歴史に関する背景知識が役立つ場面があります。
3. 2025年問題の詳細分析
3.1 第1問:長文読解(2パッセージ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | (A)トースターと標準化された食パンの文化論 (B)意見とコミュニティの関係 |
| 語数 | 合計約800語 |
| 設問形式 | 空所補充14問(語彙・文脈理解) |
| 特徴 | (A)は日常的な道具から文化論へ展開する哲学的エッセイ。”repudiating”など高度な語彙。(B)は古代レトリック論を引用した議論 |
| 難易度 | 難。抽象的な議論の理解と高度な語彙力が必要 |
3.2 第2問:長文読解(3パッセージ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | (A)グラミン銀行と貧困削減 (B)多文化主義からポピュリスト・ナショナリズムへ (C)ハーレムで育った著者の母親の夢 |
| 語数 | 合計約1,200語 |
| 設問形式 | 内容一致・推論10問 |
| 特徴 | 社会問題、政治思想、個人的体験という異なるジャンルの文章。”cosmopolitanism”、”xenophobic”など社会科学系語彙が多数 |
| 難易度 | やや難~難。多様なテーマへの対応力が必要 |
3.3 第3問:文挿入問題(ガスライティング)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | ガスライティング(心理的操作)の定義と仕組み |
| 語数 | 約1,000語 |
| 設問形式 | 文挿入7問(8つの選択肢から7つを選び適切な位置に挿入) |
| 特徴 | 心理学・哲学的な内容。論理的なつながりを理解する必要がある |
| 難易度 | 最難関。段落間の論理関係の把握が必須 |
3.4 第4問:会話文
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 友人への誕生日プレゼント選び |
| 語数 | 約300語 |
| 設問形式 | 空所補充7問(13の選択肢から選択) |
| 特徴 | “hang out”、”coming up”、”run them by you”など日常会話表現 |
| 難易度 | 標準。口語表現の知識が必要 |
3.5 第5問:要約完成(記述式)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 理性(rationality)の現代的位置づけ |
| 語数 | 約250語 |
| 設問形式 | 4~10語で要約文を完成させる記述問題 |
| 特徴 | Steven Pinkerの著作から。”Rationality is uncool”という逆説的な議論 |
| 難易度 | 難。的確な要約力と語彙選択が必要 |
4. 時間配分と試験中の戦略
4.1 セクション別の時間配分
合格者向けの指導では次のような時間配分が推奨されています。
• 大問Ⅰ(25分) — 2〜3本の中長文を素早く読み、空欄の前後で意味が合う語を選択します。語彙に自信がない場合でも文脈読みで対応できます。
• 大問Ⅱ(20分) — 3本の長文を読み、各段落ごとの主張を意識して設問に答えます。難しい単語は無視しても大意を捉える訓練をしておきましょう。
• 大問Ⅲ(15分) — 論理の流れを意識しながら各選択肢を素早く吟味します。時制や代名詞に注目して、明らかに合わないものを消去してから検討すると時間を節約できます。
• 大問Ⅳ(10分) — 会話の流れを重視しつつ、口語表現を確認。定冠詞や代名詞の指す内容が自然かどうかを判断材料にします。
• 大問Ⅴ(10分) — 要約は最後の10分を確保。本文全体の「キーとなる文」を探し、与えられた冒頭文と同じ時制・視点で短くまとめます。時制の指示がある場合には必ず従い、筆者の主張を含めることを忘れないよう注意します。
4.2 試験中の優先順位と解き進め方
• 先に易しい問題を片付ける — 合格者の体験談では、大問Ⅱや大問Ⅳなど素直な問題から取り組み、最後に要約に時間を回す方法が効率的とされています。
• 「捨て問」を決める — 毎年2〜3問程度、非常に難解な語や背景知識を要する問題が出ます。8割得点を狙うためには難問に固執せず他の問題で確実に得点する戦略が推奨されています。
• チェックポイントを意識する — 脱文補充では時制・主語・代名詞・論理マーカーを、会話文では前置詞や動詞の意味を、要約では主旨と構成を意識しましょう。
5. 大問別攻略法
5.1 大問Ⅰ:長文空所補充
• 単語・熟語の基礎を固める — 標準的な語彙で解ける問題が多いものの、年度によって “repudiate” や “denigrate” のような難単語も出ます。まずは基本単語帳を一冊完璧に覚え、同義語・反意語も整理しておきます。
• 文脈推測力 — 空欄の前後の文を読み、語彙よりも文脈やコロケーションで判断する練習をします。選択肢が紛らわしい場合は主語や時制の不一致に注目すると消去しやすいです。
• 速読力養成 — 大問Ⅰには複数の長文が出るため、読み飛ばしの練習が不可欠です。長文読解の参考書を使い、文章構造を意識して段落ごとに要約する習慣をつけましょう。
5.2 大問Ⅱ:長文読解
• 言い換え表現に慣れる — 問題文では “postpone” でも選択肢では “put off” のように言い換えてあるケースが多い。英単語を単独で覚えるのではなく、同義語・反義語・派生語をまとめて覚えておくと選択肢の判断が速くなります。
• 段落ごとにテーマを把握 — 各パラグラフにつき1問の設問が出ることが多い。読み進めながら「この段落の主張は何か」をメモし、対応する設問を処理します。
• 外部試験の問題に慣れる — 英検やTEAPなどの読解問題と形式が似ているため、これら外部試験の問題集で演習すると選択肢の作り方に慣れます。
5.3 大問Ⅲ:脱文補充
• 論理構造を意識する — 主語や時制、論理マーカー(however, therefore, または代名詞の指示対象)をチェックし、入るべき文の特徴を絞り込みます。
• 形式的手掛かりで解く訓練 — ネット上では「文章が難しい」と感じる受験生が多いものの、満点を取る受験生は本文の細部を読まず時制や代名詞など形の手掛かりで解答しています。2023年実施の解答例では、各空欄の正答を導くポイント(時制、代名詞、論理マーカーなど)をまとめることで10分以内に解けると示されています。
• 主語の連続性に注意 — 前後の文で主語が誰なのか、代名詞が何を指すかを見逃さないようにしましょう。主語が連続するかどうかが正解の決め手になることが多い。
5.4 大問Ⅳ:会話文補充
• 熟語・句動詞の知識 — “put up with”, “take out”, “run ~ by …” など口語的な句動詞が出題されるため、熟語集で意味と用法を覚えます。
• 文脈推論 — 会話には質問と回答、同意・反論など流れがあります。選択肢の機能(賛成・反対・提案など)を考慮し、自然な流れになるものを選びます。知らない表現でも動詞や前置詞の意味から推測する姿勢が重要です。
• 敬語やカジュアル表現の差 — 登場人物の関係(友人・目上など)によって使われる表現が変わることがあります。過去問で慣れておきましょう。
5.5 大問Ⅴ:英語要約
• 主旨把握の訓練 — 要約は本文の核心文を見抜く力が必要です。大意をなんとなくまとめるのではなく、筆者が伝えたい主張と理由を抽出し、自分の言葉で短くまとめます。
• 語数内で収める技術 — 指定語数(4〜10語)を超えないよう、必要のない形容詞や副詞は削り、内容語(動詞・名詞)で骨格を作ります。2024年度は9語で書く問題があり、時制や立場を正しく選ぶことが求められました。
• 表現の言い換え練習 — 本文の語句をそのまま使うと減点されるため、同義語やパラフレーズを習得しましょう。例えば “I do not understand…” を “You cannot make sense” に言い換えるなど。
6. 語彙・文法・読解の学習法
6.1 単語・熟語の覚え方
• 基本語彙の一冊を完璧に — 「システム英単語」「東大英単語熟語 鉄壁」「英単語ターゲット1900」などを推奨しています。どれでもよいので一冊を徹底的にやり切り、同義語・反意語・派生語もまとめて覚えます。
• 熟語集で句動詞を網羅 — 「解体英熟語」は前置詞のイメージとともに熟語を体系的に学べる一冊で、会話問題でも未知の表現を推測する力がつきます。
• 上級語彙対策 — 英検準1級レベルの単語帳『パスタン』(でる順パス単)を薦めています。頻出度の高いランクA~Cを中心に学習し、長文中のレア単語が出ても推測できる余裕を持ちましょう。
6.2 文法と語法
• スクランブル英文法・語法 — 正誤問題や空欄補充を豊富に収録し、解説も充実しているため、基礎から応用まで網羅できます。
• 長文の中で文法を確認 — 単独の文法問題集に加え、長文読解中に文構造を意識しながらSVOCや関係詞の働きを確認する習慣を付けると、脱文補充で文の機能を捉えやすくなります。
6.3 長文読解と速読
• やっておきたい英語長文500 — 河合塾の『やっておきたい英語長文500』は文化構想学部レベルに合致しており、語数も近い。週に数本解き、復習では20回程度音読することで速読と精読の両方を鍛えます。
• 難関大英語長文講義の実況中継 — 入試問題を講義形式で解説し、文構造の取り方を徹底的に学べるため、脱文補充や要約の基礎作りに有効です。
• 復習重視 — 「問題を解くことよりも復習と解説理解が実力につながる」と強調されています。解答後は必ず本文を精読し、知らなかった語句や表現をまとめて覚えましょう。
6.4 要約トレーニング
• 和英・英英要約の両方を練習 — 英文要約は日本語で要約した後、英語にするステップを踏むとわかりやすい。短くまとめる練習として、新聞やTEDトークの要約を7〜8語程度で表現するなど日常的に行います。
• 接続詞や論理マーカーを把握 — 要約では内容の骨組みを追う必要があるため、however, therefore, on the other hand など論理マーカーの役割を意識しながら読みます。
7. 2026年の出題予想と対策
7.1 予想される出題傾向
過去数年の安定した形式と、2025年度の難化ポイントを踏まえると、2026年度も大きな構成変更はないと考えられます。予想されるポイントは次の通りです。
• 要約問題の重要性が継続 — 2024年度から難度が上昇している要約問題は、引き続き受験生の差をつける役割を担う可能性が高い。筆者の主張や原因・結果関係を的確にまとめる力が試されるでしょう。
• 語彙レベルの少しの上昇 — 2025年度に出た”repudiate”や”denigrate”のように、一部の問題で辞書レベルの語が出題される傾向が続くと予想されます。英検準1級〜1級レベルの単語も押さえておくと安心です。
• 論理構造を問う問題 — 脱文補充では時制や主語の一貫性を見抜く力が重視され続けるでしょう。日本語の小論文のように、主張・理由・例という構造を意識すると判断しやすくなります。
• 会話文での表現の幅 — 会話問題ではチャット形式やメール形式など多様な媒体が出題される可能性も考えられます。カジュアルな句動詞や略語(e.g., “gonna”, “ASAP”)に慣れておくと対応しやすいでしょう。
7.2 2026年度に向けた学習計画
• 基礎固め(〜秋まで) — 春から夏は単語帳・熟語帳を一冊やり切り、文法・語法を「スクランブル」などで総ざらいします。長文読解では毎週2〜3本解き、速読と精読をバランスよく練習します。
• 過去問演習(秋〜冬) — 過去問は早めに着手し、文学部の過去問も併用するとよい(形式が似ているため)。最初は時間を気にせず精読し、解説を読み込んでから再度解き直します。
• 要約特訓(冬〜直前期) — 文化構想学部の過去問の要約問題を繰り返し解き、7〜9語で要点をまとめる練習をします。英検1級の要約問題や国際教養学部の要約問題も参考になります。
• 模試や外部試験の活用 — TEAPや英検など4技能試験を受験し、英文読解とライティングのフィードバックを得ることで総合力を向上させます。取得したスコアは4技能併用型入試でも利用できます。
8. 推奨教材一覧
| 学習領域 | 教材 | 特徴 |
|---|---|---|
| 単語 | 『システム英単語』/『英単語ターゲット1900』/『東大英単語熟語鉄壁』 | 同義語・反意語まで体系的に覚えられる。 |
| 『英検準1級 でる順パス単』 | 英検準1級レベルの語彙習得用。頻出度順になっており、難単語対策に最適。 | |
| 熟語 | 『解体英熟語』 | 句動詞や前置詞のイメージを理解でき、会話問題の推測力が養える。 |
| 文法・語法 | 『スクランブル英文法・語法』 | 入試頻出事項を網羅し、詳しい解説付き。 |
| 長文読解 | 『やっておきたい英語長文500』 | 早稲田の長文レベルに近い。音読・速読用に最適。 |
| 『難関大英語長文講義の実況中継』 | 長文の構造を解説しながら読める講義形式。 | |
| 脱文補充対策 | 『英文ハイレベルパラグラフリーディング』など | パラグラフリーディングの問題集で論理構造を訓練。 |
| 要約対策 | 文化構想学部の過去問/英検1級ライティング問題集 | 要約問題が豊富で、文数制限のトレーニングに適している。 |
9. まとめ
早稲田大学文化構想学部の英語試験は、5題構成で読解力・語彙力・論理力・要約力の総合力を問う試験です。過去3年(2023〜2025年)の傾向を見ると、全体の難易度は「標準レベル」で安定しているものの、要約問題の難度が上がっていること、長文の語数が多く速読力が重要であることが読み取れます。2026年度も同様の形式が続くと予想されるため、基礎固めと過去問演習を徹底し、要約と脱文補充の練習に時間を割きましょう。
多くの受験生が迷うのは難語や未知の表現に出会ったときですが、文脈や論理構造を手掛かりに消去法で解く技術を身につければ合格点に十分届きます。語彙・熟語の暗記には定評ある単語帳を一冊完璧に仕上げ、長文読解の参考書で速読力を養い、要約トレーニングでは短く要点をまとめる力を磨いてください。早期に準備を始め、余裕をもって過去問・模試に取り組めば、文化構想学部の英語で8割得点を達成する道筋が見えてくるはずです。