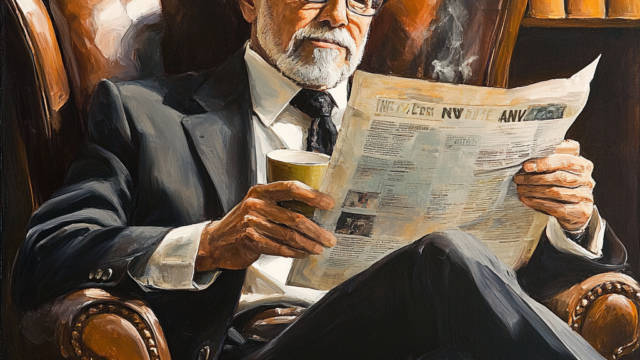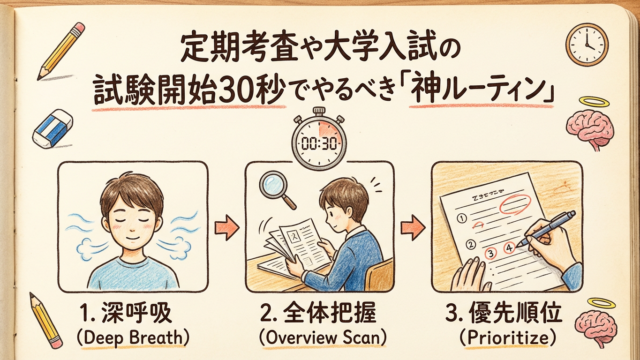2026年度の大学入試まで残りわずか。難関大学の英語長文読解で高得点を狙うなら、「どんなトピックが出題されるか」を事前に把握することが重要です。
そこで今回、英国の権威ある新聞「The Guardian」の2024年9月から2025年7月まで(大学教授が最も試験の題材に記事を選ぶ期間)の記事を徹底分析し、早慶上智、GMARCHなどの難関大学で出題される可能性の高いトピックを15本厳選しました。
なぜガーディアン紙なのか?
ガーディアン紙は、日本の大学入試英語長文で頻繁に引用される英字新聞の一つです。科学的根拠に基づいた客観的な報道と、複雑な社会問題を多角的に論じる記事の質の高さが、入試問題作成者に評価されています。
2026年入試で最注目のトピックは?
分析の結果、最も出題可能性が高いのは「マイクロプラスチックの人体への影響」でした。人間の脳内でマイクロプラスチック汚染が急激に進んでいるという研究結果が複数記事で報じられており、環境問題と健康科学を結びつける典型的な入試テーマです。
続いて注目すべきは「AI技術が人間社会に与える影響」。ChatGPTなどの生成AIが労働市場や人間の認知能力に与える影響を論じた記事が上位を占めています。「AI倫理」「技術失業」「創造性の危機」といったキーワードは、理系・文系を問わず必修と言えるでしょう。
効率的な活用法
本記事では、各トピックについて「なぜ入試に出やすいのか」「どのような設問が予想されるか」を詳しく解説。さらに実際のガーディアン紙記事への直リンクも掲載しているため、今すぐ原文を読んで実戦的な読解練習を始められます。
毎日1本ずつ英文記事を丁寧に読み進めれば、たった2週間で2026年度入試の英語長文対策を大きく前進させることができます。背景知識や入試頻出の時事英語表現を効率よく身につけ、周りとの差を広げましょう。
ただし、「The Guardian」の記事は受験生にとって難しい内容も多く含まれています。そこで、ChatGPTやDeepLなどのツールを活用した読み方のコツも解説しています。詳しくは下記の記事をご覧ください。
🏆 1位: Levels of microplastics in human brains may be rapidly rising
(人間の脳内マイクロプラスチックが急増している可能性)
概要: 1997年から2024年にかけて人間の脳内のマイクロプラスチック汚染が急激に増加していることを解剖サンプルの分析で明らかにした研究報告。脳だけでなく肝臓や腎臓でもプラスチック片が検出されており、認知症などの神経疾患への影響が深刻に懸念されている。
試験に出るチェック: 高 – マイクロプラスチック汚染と健康リスクの関係性を科学的データで示した記事。環境問題と人体への影響を結びつける典型的なテーマで、内容一致問題や因果関係を問う設問に最適。
出典直リンク: Guardian記事を読む
🥈 2位: Microplastic contamination in 99% of seafood
(シーフードの99%にマイクロプラスチックが混入)
概要: 182のシーフードサンプルのうち180で微小プラスチックが検出され、特にエビなど甲殻類で高濃度の汚染が確認された。衣服の繊維に由来するマイクロファイバーが最も多く、食料安全保障と海洋汚染の深刻な関係を浮き彫りにしている。
試験に出るチェック: 高 – 食品安全と環境問題の結び付きを具体的なデータで示す。「人間活動が海洋に及ぼす影響」を扱う長文読解問題の定番テーマで、統計データの読み取りも含まれる。
出典直リンク: Guardian記事を読む
🥉 3位: Microplastics block blood vessels in mice brains
(マイクロプラスチックがマウスの脳内血流を阻害)
概要: 動物実験でマイクロプラスチックが血管に詰まり、交通事故のように滞留して脳の血流を減少させ、運動機能の低下を招くことが判明。プラスチックがBPAやフタル酸エステル、PFASなどの有害化学物質を運ぶ可能性も指摘されている。
試験に出るチェック: 高 – 微小プラスチックの健康影響を動物実験で実証した科学的研究。実験方法と結果の因果関係を問う問題や、環境汚染と健康リスクの橋渡しとなる内容。
出典直リンク: Guardian記事を読む
4位: Workers losing jobs to AI
(AIによって仕事を失う労働者たち)
概要: ラジオ番組の司会者がAIキャラクターに置き換えられた具体的事例を通じて、AI技術が雇用を奪い深刻な倫理的問題を引き起こしている現状を報告。労働市場の変化と社会的影響を詳細に分析している。
試験に出るチェック: 高 – AIと雇用の倫理問題という現代社会の核心的課題。経済と倫理を考察する英文読解の典型的題材で、賛否両論を問う設問や社会的影響を論じる問題に適している。
出典直リンク: Guardian記事を読む
5位: Is generative AI harming human intelligence?
(生成AIは人間の知能を低下させるのか?)
概要: AIにタスクを委ねることで人間の創造性や認知力が低下する可能性を多角的に議論。フリン効果(知能検査の点数の長期的上昇)の停滞や逆転現象、専門家による「AIが人間の知能を蝕む」という懸念を詳しく紹介している。
試験に出るチェック: 高 – AIによる認知力低下への懸念という学際的テーマ。AI依存の弊害を議論する出題が予想され、批判的思考力を問う設問に最適。
出典直リンク: Guardian記事を読む
6位: Why are creatives fighting UK government AI proposals on copyright?
(英国政府のAI著作権法案に創作者が反発する理由)
概要: 英国政府が提案する「AI企業に著作権保護された作品のテキスト・データマイニングを許可する」政策に対し、音楽家や作家など約4万8千人が反発。AIモデル訓練のための作品無断使用への抗議と、適切な補償・権利保護を求める動きを詳述。
試験に出るチェック: 中 – 著作権とAIの訓練データをめぐる論争という新しい法的・倫理的課題。知的財産権とテクノロジーの関係を問う現代的なテーマ。
出典直リンク: Guardian記事を読む
7位: Tesla’s robotaxi rollout falters
(テスラのロボタクシー導入が頓挫)
概要: テスラがテキサス州オースティンで開始したドライバーなしのタクシーサービスで交通違反やトラブルが相次ぎ、米運輸省道路交通安全局の調査対象となった事例を報告。自動運転技術の現実的な課題と法規制の遅れを浮き彫りにしている。
試験に出るチェック: 中 – 自動運転の問題点と規制という技術と社会の関係を問う好例。テクノロジーの理想と現実のギャップを考察する題材として適している。
出典直リンク: Guardian記事を読む
8位: Lunar Trailblazer mission aims to map water on the Moon
(月の水を地図化する「ルナ・トレイルブレイザー」計画)
概要: 英国と米国の研究者が進める月探査計画で、水の存在場所と移動パターンを小型探査機で地図化する取り組みを紹介。月の水は将来の基地建設に不可欠で、分解による水素燃料や酸素の生成など多様な利用方法が議論されている。
試験に出るチェック: 中 – 宇宙探査と人類の未来という受験英語で人気の高いテーマ。宇宙開発と資源利用を絡めた内容で、科学技術の応用を問う設問に適している。
出典直リンク: Guardian記事を読む
9位: International Space Station’s sterile environment harming astronauts
(国際宇宙ステーションの無菌環境が宇宙飛行士の健康を害している)
概要: 国際宇宙ステーションでは土壌や水の微生物がほとんど存在せず、宇宙飛行士の免疫系が弱まり肌荒れや感染症が増加することが研究で判明。専門家は地球環境を模倣するため、あえて微生物を導入することを提案している。
試験に出るチェック: 中 – 微生物と免疫の関係という生物学的テーマ。宇宙環境が人体に与える影響は科学的興味を引く題材で、因果関係を問う設問に適している。
出典直リンク: Guardian記事を読む
10位: The experts: neurologists on 17 simple ways to look after your brain
(脳を健康に保つ17の方法 – 神経科医のアドバイス)
概要: 神経科医たちが脳の健康維持には全身の健康管理と同じ原則が重要であると助言。適度な運動、バランスの良い食事、十分な睡眠に加え、禁煙・節酒、週3回の有酸素運動、地中海食、規則正しい睡眠などの具体的な方法を提示している。
試験に出るチェック: 中 – 健康科学・ライフスタイルという身近なテーマ。受験生の健康管理にも直結する内容で、実用的な情報を含む読解問題に適している。
出典直リンク: Guardian記事を読む
11位: Owning dog or cat could preserve some brain functions as we age
(犬や猫を飼うと加齢による脳機能低下が抑えられる可能性)
概要: ヨーロッパの長期調査分析により、犬を飼う人は即時記憶と遅延記憶が良好で、猫を飼う人は言語流暢性の低下が遅いことが判明。魚や鳥を飼う場合には同様の効果は見られなかった。
試験に出るチェック: 中 – ペットと認知症予防という高齢社会に関連するテーマ。動物と人間の関係、社会的な絆の重要性を考える良い素材。
出典直リンク: Guardian記事を読む
12位: Lack of access to antibiotics is driving spread of superbugs
(抗生物質へのアクセス不足がスーパーバグの拡大を促進)
概要: 低所得国では薬剤耐性菌に感染した人のうち適切な抗生物質を入手できる割合が平均6.9%にすぎず、これが耐性菌の拡大を招いている現状を報告。医療格差が世界的な健康危機を悪化させている構造的問題を指摘。
試験に出るチェック: 中 – 医療格差と薬剤耐性という国際的な健康問題。グローバルな医療政策と格差問題を結びつけるテーマで、社会問題を扱う長文に適している。
出典直リンク: Guardian記事を読む
13位: Superbugs could kill millions more and cost $2tn a year by 2050
(2050年までにスーパーバグが数百万人を殺し、年間2兆ドルの損失をもたらす恐れ)
概要: 英政府資金による研究で、薬剤耐性が進行すると2050年までに世界のGDP損失が1.7兆ドルに達し、米国・英国・EUが最も大きな打撃を受けると試算。援助削減が耐性菌対策を弱め、最悪のシナリオでは数百万人が死亡し医療費も急増すると警告。
試験に出るチェック: 中 – AMR(抗菌薬耐性)がもたらす健康・経済への影響という複合的テーマ。医療政策や国際協力の視点を絡めた出題が予想される。
出典直リンク: Guardian記事を読む
14位: US doctors rewrite DNA of infant with severe genetic disorder in medical first
(重度の遺伝性疾患を持つ乳児のDNAを書き換えた米国の医師たち – 医学の初の快挙)
概要: 米国の医師団が致死性の高いCPS1欠損症の乳児に対し、個別に設計した遺伝子編集療法を世界で初めて実施。患者の遺伝子変異を特定し、ベース編集技術でDNAの一文字を修正する治療を半年で開発し、乳児は3回の投与後に順調に成長している。
試験に出るチェック: 中 – ゲノム編集の最前線という先端医療技術のテーマ。遺伝子治療の新時代を告げる成果で、科学技術の進歩と倫理的議論を含む出題が考えられる。
出典直リンク: Guardian記事を読む
15位: ‘Global weirding’: climate whiplash hitting world’s biggest cities
(「グローバル・ウィアーディング」:気候の極端な揺れが大都市を襲う)
概要: 大都市で乾季と洪水が急激に切り替わる「気候ウィップラッシュ」現象を報告。112の都市のうち95%が乾燥化または湿潤化の傾向を示し、都市の水インフラや食料供給、健康に深刻な影響を与えている。急激な干ばつと豪雨を繰り返す都市では準備と復旧が困難で、農作物や家畜への被害が連鎖している。
試験に出るチェック: 中 – 気候変動と都市の水資源という環境問題の新しい側面。気候変動の不均一な影響を扱う好例で、都市化と環境問題を結びつけるテーマ。
出典直リンク: Guardian記事を読む
📊 まとめ
これらの記事は、マイクロプラスチック汚染、AI技術の社会的影響、宇宙開発、医療技術の進歩、気候変動という5つの主要テーマに分類されます。
特に上位5記事は、現代社会が直面する最も深刻な課題を科学的根拠とともに論じており、難関大学の英語長文読解問題として高い出題可能性を持っています。これらのトピックに関する背景知識と関連語彙の習得が、2026年度入試成功の鍵となるでしょう。
Guardian記事から厳選した!大学入試に超絶出る時事英単語BEST100
2026年入試 要注意トピック【追加15選】