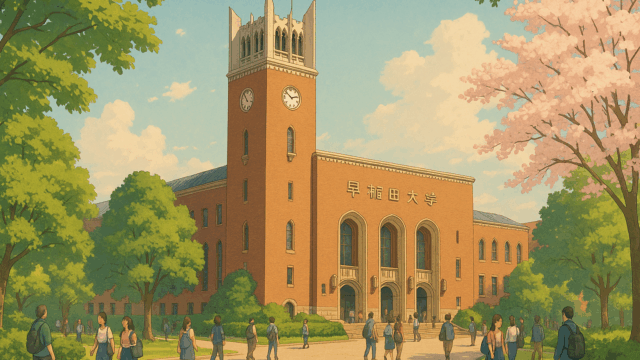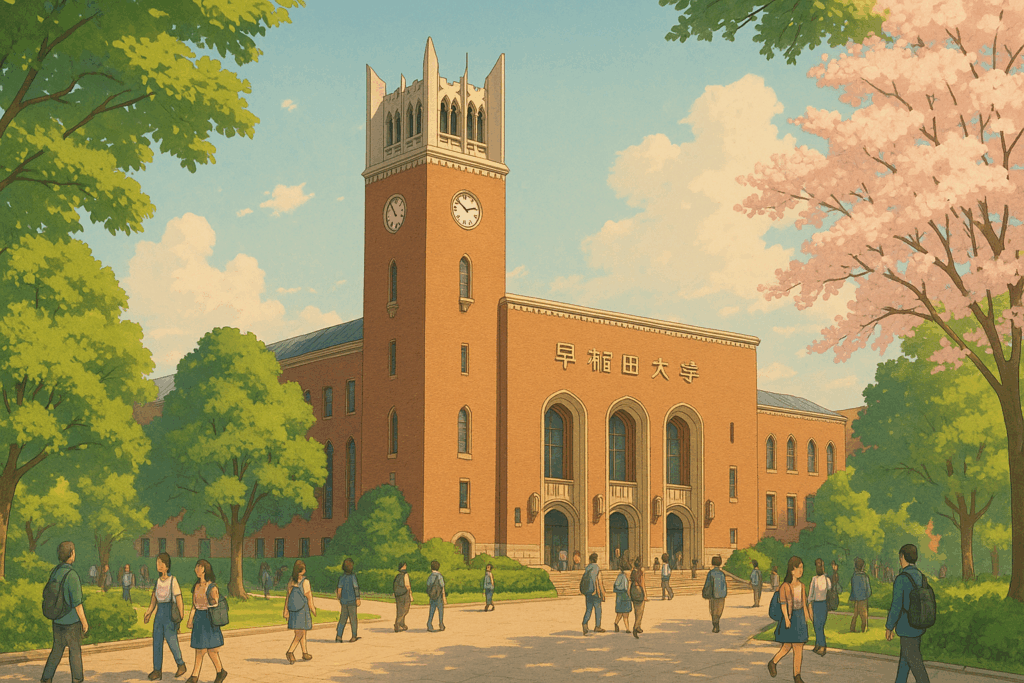
はじめに
2025年度(令和7年度)に実施された早稲田大学文学部・文化構想学部の入学試験では、従来どおり英語の第5問として「英文要約」が出題されました。2024年度頃からこの要約問題の難度が上がっており、2025年度は「4〜10語で要約を完成させる」「本文中の語句をそのまま使うことは禁止」という制約の中で、筆者の主張や論理展開を的確にまとめる力が強く問われました。
2025年度の要約問題を研究する
| 学部 | テーマ | 本文の趣旨 | 要約形式 |
|---|---|---|---|
| 文化構想学部 | 理性は“ダサい”? (Rationality / Steven Pinker) |
合理性が「格好悪い」とされながらも、それに従うべきだとする主張。 映画やロックの歌詞では理性否定が賛美され、ポストモダニズムによる批判も登場。 理性を擁護する姿勢を強調。 |
“Rationality has typically been seen as …” に続けて4〜10語で要点を示す。 |
| 文学部 | 心の“さまよい”は欠陥ではない (Talking Heads / Shane O’Mara) |
注意散漫が危険な場面もあるが、創造的活動には有益。 現代科学は「心のさまよい」を脳の特徴と捉えており、場面に応じた評価が重要。 |
“Modern science argues that mind wandering is not a defect …” に続けて4〜10語でまとめる。 |
出題傾向と難化ポイントの分析
| 分析項目 | 詳細 |
|---|---|
| 形式の安定 | 2010年代以降、5題構成で一貫。 空所補充・長文読解・脱文補充・会話文・英文要約。 |
| 要約問題の難化 | 語数指定+語句使用制限により、論理構成力・言い換え力が求められる。 |
| 語彙レベル上昇 | “repudiate” や “denigrate” など英検準1級以上の難語が出題。 |
| 論理構造重視 | 接続詞や指示語に注目し、時制・主語の整合性から論理展開を読み取る力が必要。 |
2026年度の出題を大胆予想
| 予想項目 | 可能性のある展開 |
|---|---|
| トピック | 認知科学→社会科学へ。生成AIの倫理・気候変動・デジタル監視社会など。 |
| 語彙・論理レベル | 抽象概念・難語が引き続き登場。論理構造の理解と速読力が重要。 |
| 会話形式 | チャット型やメール型など多様なスタイルへ。略語・口語への慣れが必要。 |
| 要約の洗練 | 特定パラグラフに基づく要約や反論の構成など、“ひねり”ある出題も想定。 |
要約問題の勉強法(7ステップ)
| ステップ | 学習内容 |
|---|---|
| ① 主旨把握 | 段落ごとに要点整理。新聞やTEDなども活用。 |
| ② 簡潔・明確 | 主語・動詞・目的語を明確に。冗長表現は省略。 |
| ③ 語彙・言い換え | 本文語句は使えないため、同義語・パラフレーズ力が必須。 |
| ④ 情報の選択 | 主要情報を選び抜き、段落ごとの「誰・何・どうした」を把握。 |
| ⑤ 和英・英英要約 | 日本語で大意を整理→英語要約で語数制限の訓練。 |
| ⑥ 模試・過去問活用 | 文学部・文化構想学部の形式を比較。冬以降は集中演習。 |
| ⑦ 教材選び | 語彙・文法・長文・要約まで、総合教材を併用。 |
おすすめ教材一覧
| 学習領域 | 教材名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 単語 | 『システム英単語』/『英単語ターゲット1900』 | 同義語・反意語まで体系的に覚えられる |
| 上級語彙 | 『英検準1級 でる順パス単』 | 頻出順で難語対策に最適 |
| 熟語 | 『解体英熟語』 | 句動詞・前置詞のニュアンス理解が可能 |
| 文法・語法 | 『スクランブル英文法・語法』 | 入試頻出項目を網羅した解説付き問題集 |
| 長文読解 | 『やっておきたい英語長文500』/『難関大英語長文講義の実況中継』 | 精読+速読練習に最適 |
| 脱文補充 | 『英文ハイレベルパラグラフリーディング』 | 論理構造のトレーニングに有効 |
| 要約対策 | 文化構想学部過去問/英検1級ライティング問題集 | 語数制限・骨格把握の訓練が可能 |
解法のテクニック(実践的アプローチ)
- 全体像の把握:まず本文に目を通し、構造とテーマをざっくりつかむ。
- 核となる文探し:論理マーカーに注目して、主張・結論文を特定。
- 言い換え語選択:動詞+名詞の骨格
【予想問題1】早稲田大学文化構想学部
■ 英語問題
Read the following passage and complete the English summary in your own words in the space provided on the separate answer sheet. The beginning of the summary is provided; you must complete it in 4-10 words. Do not use three or more consecutive words from this page.
Curiosity is undervalued. To label someone as inquisitive or nosy often suggests they are intrusive or overly prying, lacking in social grace. For years, literature and media have portrayed contentment and serenity as arising from acceptance without question. “Ignorance is bliss,” goes the old adage, echoed in countless stories where probing too deeply leads to downfall. “Let sleeping dogs lie,” advise proverbs; “Don’t rock the boat,” caution elders. Prominent intellectual trends like minimalism and mindfulness emphasize living in the moment, implying that constant questioning disrupts inner peace and harmony. These ideas carry a veneer of wisdom, suggesting that relentless curiosity is naive, disruptive, or even harmful to societal norms across eras and societies. Indeed, not far from my office in a bustling city library, there is an ornate plaque that reads, “Seek knowledge.” But it adorns the entrance to a historical society known more for preserving traditions than challenging them, which some view as the antithesis of bold exploration.
My stance on curiosity is straightforward: “Embrace it.” Although I cannot claim that questioning everything is always comfortable, and I won’t attempt to glamorize it beyond its merits, I will advocate for the inscription on that plaque: we should pursue inquiry.
(Adapted from Elizabeth Gilbert, Big Magic)
SUMMARY:
[complete the summary on the separate answer sheet]
Curiosity has generally been regarded as …
■ 解答
Curiosity has generally been regarded as intrusive or disruptive to harmony.
■ 解説
| 解法のポイント |
|
| キーワード抽出 |
|
| 語数確認 | intrusive (1), or (2), disruptive (3), to (4), harmony (5) → 5語(規定の4-10語内) |
■ 日本語訳
【問題文の日本語訳】
以下の英文を読んで、別紙の解答欄に自分の言葉で英語の要約を完成させなさい。要約の始めは与えられているので、それを4-10語で続けなさい。このページから3語以上の連続した言葉を使わないこと。
好奇心は過小評価されている。誰かを詮索好きやおせっかいと呼ぶのは、しばしば彼らが干渉的で過度に詮索し、社会的な優雅さに欠けることを示唆する。長年にわたり、文学やメディアは、疑問を抱かずに受け入れることから満足と平穏が生まれると描いてきた。「無知は幸福」という古い格言があり、深く探求しすぎると転落を招くという無数の物語で繰り返されている。「寝ている犬を起こすな」と諺は忠告し、「波風を立てるな」と年長者は注意する。ミニマリズムやマインドフルネスのような著名な知的トレンドは、現在に生きることを強調し、絶え間ない疑問が内なる平和と調和を乱すことを示唆する。これらの考えは叡智の装いをまとい、執拗な好奇心が単純で、破壊的で、時代や社会を超えて社会規範に有害であることさえ示唆する。実際、賑やかな都市の図書館にある私のオフィスからそう遠くないところに、「知識を求めよ」と書かれた華麗な銘板がある。しかし、それは伝統を保存することで知られる歴史協会の入り口を飾っており、一部の人々はそれを大胆な探求の正反対と見なしている。
好奇心に対する私の立場は単純明快だ:「それを受け入れよ」。すべてを疑問視することが常に快適だとは主張できないし、その価値以上に美化しようとも思わないが、私はその銘板の文言を擁護する:私たちは探求を追求すべきだ。
【解答の日本語訳】
好奇心は一般的に干渉的または調和を乱すものと見なされてきた。
【予想問題2】早稲田大学文学部
■ 英語問題
【5】Read the following passage and complete the English summary in your own words in the space provided on the separate answer sheet. The beginning of the summary is provided; you must complete it in 4-10 words. Do not use three or more consecutive words from this page.
We have all encountered moments where our thoughts stray during routine activities, like reading a monotonous report. Daydreaming can prove risky in high-stakes scenarios; if your focus lapses while operating machinery, it could result in serious accidents. Allowing thoughts to roam in a lecture hall is milder: the consequence might be a gentle reprimand from an instructor. We oscillate between intense focus on specifics and broader reflections, perhaps pondering long-term goals. A central insight from contemporary neuroscience is that daydreaming defines human cognition. It ought not to be viewed as a flaw in our mental architecture.
Daydreaming hinders activities needing sustained attention, yet it boosts those involving innovation and resolution: for a writer, it can impair precision in editing dense prose or crafting intricate plots. Maintaining sharp awareness of nuances, correctly depicted, would falter if the writer’s focus drifts, causing inconsistencies in the narrative. Nevertheless, daydreaming aids in generating fresh ideas, like plotting an original story or devising metaphors, via unexpected associations of concepts and memories. Likewise, in scientific research, it can obstruct meticulous data analysis or conducting experiments, but advantageous for hypothesizing novel theories, frameworks, or discoveries.
(Adapted from Daniel Levitin, The Organized Mind)
SUMMARY:
[complete the summary on the separate answer sheet]
Contemporary neuroscience posits that daydreaming is not a flaw …
■ 解答
Contemporary neuroscience posits that daydreaming is not a flaw but inherent to cognition with benefits.
■ 解説
| 解法のポイント |
|
| キーワード抽出 |
|
| 語数確認 | but (1), inherent (2), to (3), cognition (4), with (5), benefits (6) → 6語(規定の4-10語内) |
■ 日本語訳
【問題文の日本語訳】
【5】以下の英文を読んで、別紙の解答欄に自分の言葉で英語の要約を完成させなさい。要約の始めは与えられているので、それを4-10語で続けなさい。このページから3語以上の連続した言葉を使わないこと。
私たちは皆、単調な報告書を読むような日常活動中に思考がそれる瞬間を経験したことがある。白日夢は高リスクの状況で危険を証明することがある;機械を操作中に集中力が途切れると、深刻な事故につながる可能性がある。講義室で思考をさまよわせるのはより穏やかだ:結果は講師からの穏やかな叱責かもしれない。私たちは具体的事項への強い集中とより広い反省の間で揺れ動き、おそらく長期目標を熟考している。現代神経科学の中心的な洞察は、白日夢が人間の認知を定義するということだ。それは私たちの精神構造の欠陥と見なされるべきではない。
白日夢は持続的な注意が必要な活動を妨げるが、革新と解決を含むものを促進する:作家にとって、それは濃密な散文の編集や複雑なプロットの作成における精度を損なうことがある。ニュアンスへの鋭い意識を維持し、正しく描写することは、作家の集中が逸れると失敗し、物語に不整合を引き起こす。それにもかかわらず、白日夢は新鮮なアイデアの生成を助ける、独創的な物語の計画や比喩の考案のように、概念と記憶の予期せぬ関連を通じて。同様に、科学研究では綿密なデータ分析や実験の実施を妨げることがあるが、新しい理論、枠組み、または発見の仮説立てには有利だ。
【解答の日本語訳】
現代神経科学は、白日夢が欠陥ではなく認知の本質的要素で利益をもたらすと主張する。