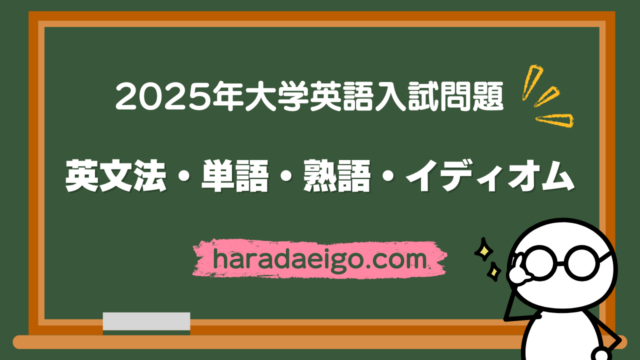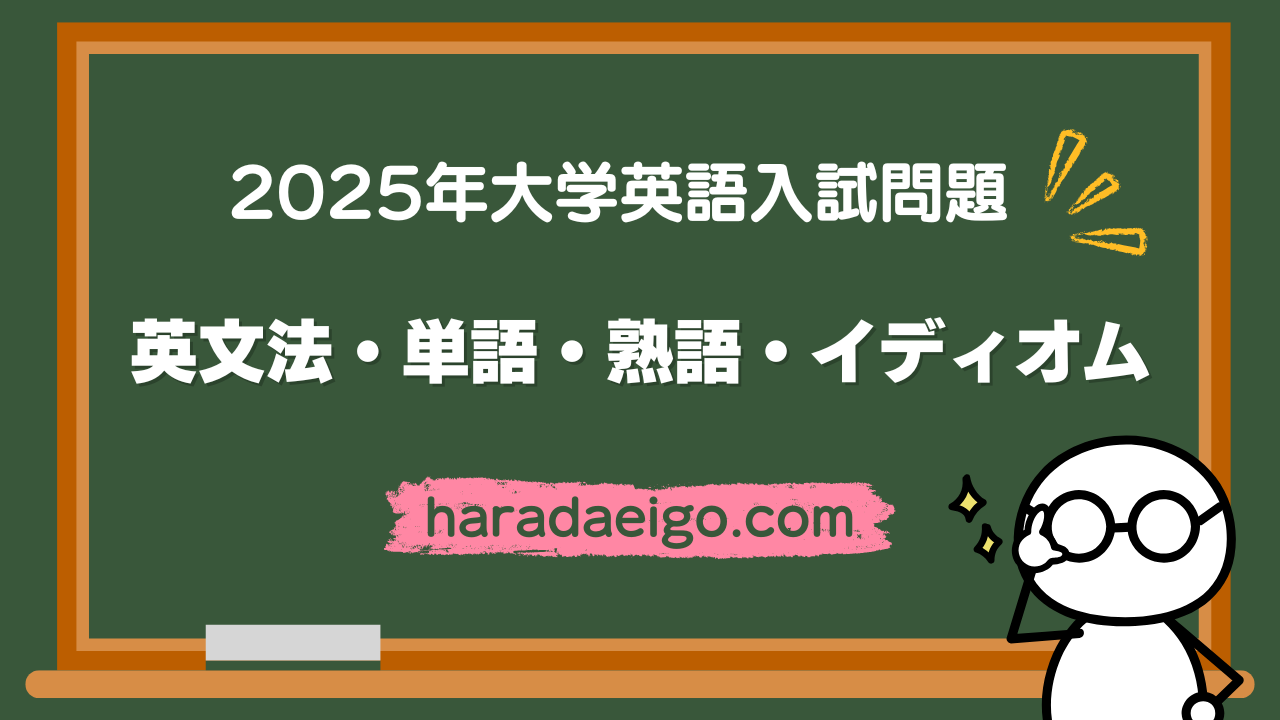
1. 【中央大学(法)2025】
Water is necessary for development and production, ( ) we are overusing and polluting this resource.
(a) despite
(b) so that
(c) unless
(d) yet
【解答】(d)
【解説】
前半「水は開発と生産に必要である」と、後半「私たちはこの資源を使いすぎ、汚染している」という内容は逆接の関係にあります。接続詞の (d) yet は「しかし、それにもかかわらず」という意味で、2つの文をつなぐのに最も適切です。
(a) despite は前置詞なので文をつなげません。(b) so that は「〜するために」という目的を表します。(c) unless は「〜でない限り」という条件を表します。
【訳】 水は開発と生産に必要ですが、それにもかかわらず私たちはこの資源を過剰に使用し、汚染しています。
2. 【中央大学(法)2025】
This data suggests Japan has a higher ( ) of people with suspected gambling disorders than other countries.
(a) association
(b) composition
(c) proportion
(d) resolution
【解答】(c)
【解説】
文脈は「このデータは、日本が他国よりもギャンブル依存症が疑われる人々の( )が高いことを示唆している」となります。「割合、比率」を意味する (c) proportion が最も適切です。”a proportion of ~” で「〜の割合」という意味になります。
(a) association「関連、協会」、(b) composition「構成」、(d) resolution「解決、決意」は文脈に合いません。
【訳】 このデータは、日本が他国よりもギャンブル依存症が疑われる人々の割合が高いことを示唆しています。
3. 【中央大学(法)2025】
The circumstances surrounding individual men and women are rapidly evolving, ( ) significant impacts on gender studies today.
(a) has
(b) having
(c) that has
(d) to have
【解答】(b)
【解説】
主節 “The circumstances … are rapidly evolving” があり、コンマの後に続いて、その結果として起こることを説明しています。これは分詞構文が使われる典型的なパターンです。「そして(そのことが)重大な影響を与えている」という能動的な意味なので、現在分詞の (b) having が正解です。
(a) has は動詞なので、接続詞なしで文をつなぐことはできません。
【訳】 個々の男性と女性を取り巻く状況は急速に変化しており、今日のジェンダー研究に重大な影響を与えています。
4. 【中央大学(法)2025】
If you need more than 30 minutes to fall asleep, you cannot feel rested ( ) the number of hours you spend in bed.
(a) corresponding to
(b) in addition to
(c) on account of
(d) regardless of
【解答】(d)
【解説】
文脈は「寝付くのに30分以上かかる場合、ベッドで過ごす時間の長さ( )、休んだ気にはなれない」となります。「〜にかかわらず、〜に関係なく」という意味を表す (d) regardless of が最も適切です。
(a) corresponding to「〜に応じて」、(b) in addition to「〜に加えて」、(c) on account of「〜のために」は文脈に合いません。
【訳】 寝付くのに30分以上必要な場合、ベッドで過ごす時間の長さにかかわらず、休んだとは感じられません。
5. 【中央大学(法)2025】
Mass production is ( ) only if its rhythm can be maintained and companies can continue to sell their products in steady quantity.
(a) abundant
(b) costly
(c) instrumental
(d) profitable
【解答】(d)
【解説】
文脈は「大量生産は、そのリズムが維持され、企業が製品を安定した量で販売し続けられる場合にのみ、( )である」となります。条件が満たされた場合に大量生産がどうなるかを考えると、「利益の上がる、儲かる」という意味の (d) profitable が最も適切です。
(a) abundant「豊富な」、(b) costly「費用のかかる」、(c) instrumental「助けとなる」は文脈に合いません。
【訳】 大量生産は、そのリズムが維持され、企業が製品を安定した量で販売し続けられる場合にのみ、利益が上がるものである。
6. 【中央大学(法)2025】
Skilled coaches remove bad habits by encouraging children to learn from their mistakes rather than from being punished ( ) them.
(a) at
(b) for
(c) of
(d) to
【解答】(b)
【解説】
“punish someone for ~” で「(人)を〜の理由で罰する」という意味になります。この受動態 “be punished for ~”(〜のことで罰せられる)が使われています。them は mistakes を指しており、「間違いのことで罰せられる」となるため、前置詞は (b) for が正解です。
【訳】 熟練したコーチは、子供たちが間違いのことで罰せられることからではなく、自らの間違いから学ぶことを奨励することによって、悪い習慣を取り除く。
7. 【中央大学(法)2025】
We could not find the house by the lake in ( ) the author was living when he finished his literary masterpiece.
(a) as
(b) that
(c) where
(d) which
【解答】(d)
【解説】
空所には、先行詞 “the house” を目的語とする関係代名詞が入ります。前置詞 “in” の目的語になるため、(d) which が正解です。”in which” で「その家の中で」という意味になり、関係副詞 where と同じ働きをします。
関係代名詞 that は前置詞の直後には置けません。
【訳】 私たちは、その作家が文学の傑作を完成させたときに住んでいた湖畔の家を見つけることができなかった。
8. 【中央大学(法)2025】
In Asia, competitive elections were ( ) after World War II, in many cases as a result of independence from colonial control.
(a) conducted
(b) devoted
(c) occupied
(d) resigned
【解答】(a)
【解説】
文脈は「アジアでは、第二次世界大戦後、競争的な選挙が( )された」となります。選挙などを「行う、実施する」という意味の動詞は (a) conduct です。ここでは受動態で使われています。
(b) devoted「捧げられた」、(c) occupied「占領された」、(d) resigned「辞任した」は文脈に合いません。
【訳】 アジアでは、第二次世界大戦後、多くの場合、植民地支配からの独立の結果として、競争的な選挙が行われた。
9. 【中央大学(法)2025】
The media have a strong interest in racial issues and poverty problems, but the intersection between them has ( ) well reported.
(a) always been
(b) always to be
(c) yet been
(d) yet to be
【解答】(d)
【解説】
“yet to be + 過去分詞” で「まだ〜されていない」という意味の定型表現です。文脈は「メディアは人種問題や貧困問題に強い関心を持っているが、両者の交差点についてはまだ十分に報道されていない」となるため、(d) yet to be が正解です。
【訳】 メディアは人種問題や貧困問題に強い関心を持っているが、それらの交点についてはまだ十分に報道されていない。
10. 【中央大学(法)2025】
The removal of trees along the street has ( ) residents angry about a lack of consultation.
(a) caused
(b) left
(c) taken
(d) urged
【解答】(b)
【解説】
“leave + O + C” で「OをCの状態のままにする、OをCの状態にさせる」という第5文型を作ります。文脈は「街路樹の伐採は、住民を協議不足について怒らせたままにした(怒らせた)」となるため、(b) left が正解です。
(a) cause は “cause O to do” の形をとります。(d) urge も “urge O to do” の形です。
【訳】 通り沿いの樹木の伐採は、協議がなかったことについて住民を怒らせた。